双極性障害は、周囲からはなかなか理解されにくい病気です。
気分が浮き沈みや言動の変化に、パートナーとしてどう向き合えばいいのか悩んでいませんか?
「こんなに支えているのに、どうしてうまくいかいないんだろう?」
「これは本当に本人の気持ち?病気のせい?」
そんな疑問や迷いを抱えるあなたに、双極性障害のパートナーとして知っておいてほしい大切な5つのポイントをお伝えします。
正しい理解が、きっとあなた自身を楽にし、お二人の関係をよりいいものにするはず!
気分の波は本人の意思でコントロールできないもの
双極性障害は「気分の波」が大きくなる病気です。
ハイテンション(躁状態)も、落ち込み(うつ状態)も、本人がわざとやっている訳ではなく、脳の働きによって自然に起きています。
当事者にもし、
「どうしてそんなに怒るの?」「そんなに元気なのに、なんで病気なの?」
と感じることがあったとしても、それは病気の一部なのです。
責めずに「今は波の時期なんだ。」と受け止めることが、お互いとって楽になります。
どうしてコントロールできないの?
双極性障害の気分の波は、性格や努力ではどうにもできない「脳の病気」によって起きていきます。
本人も「こんなに気分でいたくない」「もう少し普通に過ごしたい」と思っていても、気分が自動に振り切れてしまうことがあります。
重要なのは、「気持ちの問題」「甘え」「わがまま」ではない、ということを理解すること。
具体例①:急に不機嫌になったとき
〜状況〜
朝は元気だったのに、夕方になると急に無気力になり、話しかけても冷たくなる。
【NG例】
「さっきまで元気だったのに、なんでそんなに機嫌悪いの?」
→本人も説明できないことが多く、責めると自己嫌悪が強まります。
【OK例】会話例
 パートナー
パートナーなんか急にしんどくなってきたのかな?話したくなったらいつでも言ってね。



…ごめん。なんでか分からないけど、急に無理になったかも。



大丈夫だよ。そういう波もあるもんね。少しそっとしておくね。
原因を無理に聞き出すことはせず、「波」を自然に受け入れる声かけが安心に繋がります。
具体例②:ハイテンションになりすぎて止まらないとき
〜状況〜
夜遅いのに、パートナーが急に掃除や趣味に没頭し、止めても聞かない。
【NG例】
「いい加減にして。もうやめなよ。」
→強く止めてしまうと、逆効果で、かえってテンションが上がってしまうリスクが上がる。
【OK例】会話例



今すごく元気な感じだね。でも夜も遅いし、一回一緒に少し休憩しない?
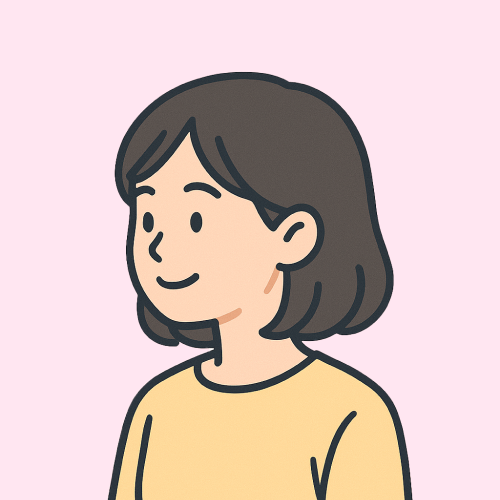
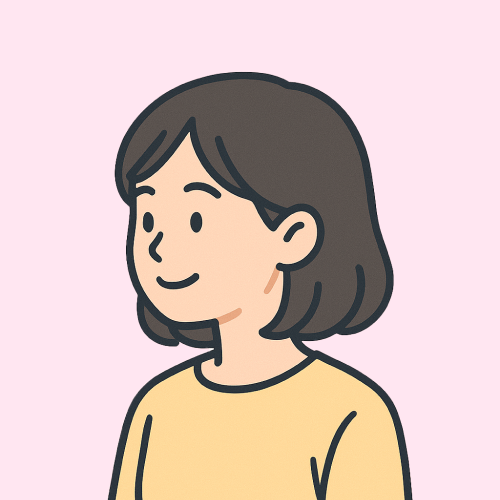
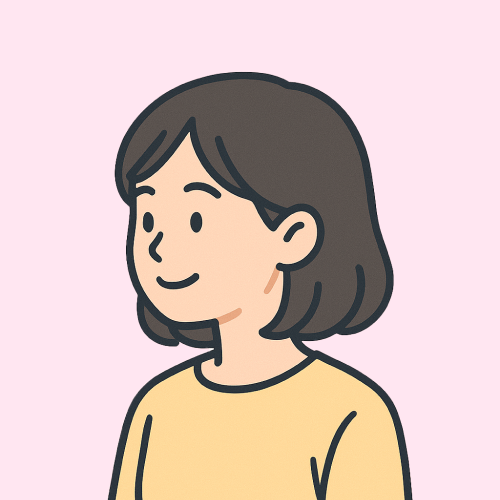
いや、今やりたいことから大丈夫だよ!!!



分かった。でも一緒に休憩したら、多分もっと気持ち続けられるかもしれないよ。
否定はせず、やっていることを一度受け入れてから、やんわりと気分を切り替える提案をする。
「あなたにだけ」きつく当たるのは、信頼している証拠かもしれません
双極性障害は、安心できる相手にだけ感情をぶつけてしまうことがあります。
辛さや苦しさを一番分かってほしい人だからこそ、つい”無防備”になってしまうのです。
もちろん、パートナーは当事者に言われたことを全部受け止めてしまうことで傷つくこともあるかもしれませんが、「本当はどう感じているんだろう?
と、一歩引いて気持ちを見つめる時間を持つこともとても大切になってきます。
どうしてパートナーにだけきつく当たるのか?
双極性障害の当事者は、一番安心できる存在にだけ、本音や弱さをぶつけやすい傾向にあるとも言われています。
・外では頑張って笑顔で振る舞う
・友人や同僚には気を遣う
・家に帰るとパートナーにだけ自分の感情をぶつける
これには、「パートナーは離れていかない」と信じているからこそ甘えてしまう面もあるのです。
もちろん、傷つくことを我慢し続ける必要はありませんが、これは「嫌われるサイン」という訳ではなく、「心を許しているサイン」ということが多いです。
具体例①:些細なことで突然怒られたとき
〜状況〜
何気なく行った一言に対して、当事者のパートナーが急に怒り出した。
【NG例】
「なんでそんなに怒るの?他の人はそんな態度取らないくせに、なんで俺だけなん?」
→比較されてしまうと、本人はますます自己嫌悪に陥り、お互いの関係が悪化し、最悪のケースだと離婚やお別れの危機にも。
【OK例】会話例



びっくりしたよ。でも、私だから安心して気持ちを出せたのかな?



…分かんないけど、他の人には言えないんだよね。



私にだけ素直になれるんだね。嬉しいよ、だけど怒りたくなるくらいしんどかったんだね。
「私にだけ怒ることは、”信頼の証”」と、ポジティブに捉えて、まずは本人の気持ちを受け入れること。
具体例②:外では普通なのに、家では不機嫌
〜状況〜
職場や友人の前では元気なのに、家では無言・冷たい態度。
【NG例】
「外ではちゃんとしてるのに、私にだけ冷たいのはおかしいよね。」
→理詰めで詰め寄ると、本人は追い詰められやすい。
【OK例】会話例



今日、外では頑張ってたんだね。疲れちゃったかな?



…うん、なんか気が張っててさ。



家では力抜いていいからね。ちょっとイライラししても大丈夫だよ。
「家=安心できる場所」と本人が思える声かえを意識する。
具体例③:ひどいことを言われて傷ついたとき
〜状況〜
感情的になった本人から、きつい言葉や傷つく言い方をされた。
【OK例】会話例



今の言い方、ちょっと傷ついちゃった。だけど、あなたがしんどいのも分かっているよ。



ごめん……。つい、あなたには言ってしまうの。



私だから言いやすいのは、ちょっと嬉しい!だけど、言い方だけ少し優しくしてくれると嬉しいな。
あなたが素直にぶつけられる存在であることを受け入れつつ、自分も傷ついていることを優しく伝えるというバランスがとても大事!
一方的に我慢をしないこと。
どんなに支えても、パートナーが「治す」ことはできません
あなたがどれだけ努力をしても、病気を「治す」ということはできません。
唯一あなたができることは、「支えること」「寄り添うこと」です。本人にとって、何よりも心の支えが何よりの治療になります。
本人が治療を頑張って続け、自分と向き合うことが回復への第一歩に繋がります。
「私が頑張れば治るはず」と、思い込んでしまうと、あなた自身が苦しくなってしまうので、決してあなたも当事者と同じように無理だけはしないで、自分の幸せも大切にしてください。
なぜ「支えること」と「治すこと」は違うのか?
パートナーは、目の前で苦しんでいる大切な人を「なんとかしたい」「助けたい」と強く思うはず。
ですが、双極性障害は本人が自分で向き合い、治療に取り組まない限り、周りがどれだけ頑張っても改善はしません。
支えることはできますが、
病気を治す
気分に波を完全に無くす
代わりに治療する
ことは、残念ながら本人以外の誰にもできないのです!
具体例①:治療をやめたがっているとき
〜状況〜
本人が「もう薬なんてやめたい、しんどいもん。」「病院に行きたくない」と言い出した。
【NG例】
「お願いだから病院行こうよ。せっかく頑張って行ってるのに勿体無いよ。困るのは自分だよ?」
【OK例】会話例



薬をやめたくなるくらい辛いんだね、しんどいもんね。



…うん、こんなに飲んでも結局意味ないし。



私はあなたに元気でいてほしいけど、無理に続けろとは言えない。だけど、あなたがどうしたいのかを一緒に考えることはできるよ。
治療を「本人の選択」として尊重しつつ、パートナーの気持ちも率直に伝える。
具体例②:うまくいかない本人を責めてしまうそうなとき
〜状況〜
再発を繰り返し、同じことが何度も起きてパートナーが疲れてきている。
【NG例】
「もう何回目?しっかりしなよ。前も同じことしてたじゃん。」
【OK例】会話例



私も何度も繰り返して、正直しんどくなっちゃう時もある。でもね、病院はすぐに良くなるものじゃないって分かってるよ。



…私も本当は嫌なんだよ。



うん、一緒に頑張りたいし、だけど私もたまにはあなたと入れるために少し休むね。
支える側も「自分限界」を正直に伝えることで、二人が良好な関係が続けられるバランスを作ることができる。
具体例③:自分が無力だと感じるとき
〜状況〜
パートナーが何もしてあげられない無力感で落ち込んでいる。
【OK例】会話例



何もできなくてごめんね。本当に自分が情けない。



いや、あなたがいてくれるだけで十分なんだよ!



本当に?私はもっとできることがあるんじゃないかって思ってる。



それは違うよ。一緒にいてくれるだけで救われてるよ。
「傍にいること」「話を聞くこと」は決して小さなことではないと実感できる会話を大切にする。
距離を取ることは「見捨てること」ではありません
辛いとき、苦しいとき、どうしようもできなくなってしまったとき、どうしても支える側も心が限界になることも少なくありません。
そんなときに、一時的に距離を当事者と取ることが必要です。
「あなたを見捨てたわけじゃない。私も休む時間が必要なんだ。」と、優しく伝えることは、お互いにとって健康的な選択なのです。
あなたの心が元気でないと、長く寄り添うことはできませんし、この病気というのは、長期的に付き合っていかなければならない病気だからです。
なぜ距離を取ることが必要なのか?
双極性障害のパートナーを支えるあなたにも、疲れるとき・しんどいとき・余裕がないときがあります。
でも、多くの人は、
・「離れたら、相手がもっと悪くなるかも」
・「私が支えなきゃ、私がいないと」
・「私が離れたら、見捨てたことになるんじゃないか」
と、自分を犠牲にしてまで寄り添おうとしてしまいます。
けれど、支える側が疲れ切ってしまうと、結果的に二人とも壊れてしまい、”共倒れ”につながってしまいます。
距離を取ることは「見捨てること」ではなく、自分を守りながら関係を続けるための大切な選択肢なのです。
具体例①:自分が限界に近いと感じたとき
〜状況〜
連日のサポートで自分も気持ちが沈み、もうパートナーに優しくできない状態。
【NG例】
(無理に笑顔で接し続けて、突然爆発してしまう)
【OK例】会話例



最近、私もちょっと気持ちがしんどくなってきてて…。あなたと向き合いたいから一回、自分の時間も増やそうと思ってるんだ。



え、私のこと嫌になったってこと?



違うよ。私はこれからも傍にいたいけど、自分の休む時間があるとあなたにきちんとサポートできなくなる気がして。
「離れたいから」ではなく、「一緒にいるために距離をとる」という説明を相手に納得がいくように伝えることで、相手も安心しやすくなります。
小さな「良かった」を一緒に見つけることが、二人の支えになる
双極性障害は、波が長く続く病気です。
完璧を目指すのではなく、日々の「今日は薬が飲めた」「今日は少し笑えた」など、ほんの小さな前進を一緒に喜ぶことが、二人の絆を強くしてきます。
お互いに「できたこと」に目を向けて、当事者にとっての小さな幸せを積み重ねていくことが、無理なく続けられる支え方です。
どうして「小さな良かった」が大切なのか?
双極性障害の当事者は、躁の時は過剰に自身を持ったり、反対にうつのときは、極端に自己否定したりと、「極端な見方」になりやすい傾向にあります。
そんなんとき、大きな目標や完璧を求め過ぎると、かえって心が折れやすくなってしまいます。
だからこそ、「今日ちゃんと薬を飲めた」「外に一歩だけ出られた」「少しだけ笑えた」
など、小さな良かったことを一緒に見つけて一緒に喜ぶことが、日々を乗り越える力になります。
具体例①:うつ状態で何もできなかった日
〜状況〜
当事者がベッドからほとんど起き上がれず、「何もできなかった…」と自己嫌悪に陥っている。
【NG例】
「気分転換に散歩くらいしたら良かったのに。」
→ 本人を追い詰めてしまうことになる。
【OK例】会話例



ううん、”薬を飲む”って、とても大切なことだよ。今日それができたって、すごい一歩じゃない?



…でも、何もしてないよ…。
「できなかったこと」ではなく、「できたこと」に意識を向けて、当事者の方に優しく声をかけること。
具体例②:躁状態でやりすぎたとき
〜状況〜
買い物をし過ぎたり、過剰に活動的になり、後から本人が落ち込んでいる。
【NG例】
「だから言ったじゃん。無理しないって約束したでしょ。」
→ 責めると本人の”自己否定”が強まる。
【OK例】会話例



あのときはすごくエネルギーに溢れてたね。今日、それにちゃんと気づいて反省できてるのは偉いよ。



…でも、何もしてないよ…。



そんなんことないよ、気づいて次に活かそうって思えるだけで、一歩前進だよ。
過去を決して責めずに、「気づけたこと」「今できていること」を肯定する。
具体例③:気持ちが安定している日
〜状況〜
特に大きな出来事はないけれど、比較的他の日よりも穏やかに過ごせた日。
【OK例】会話例



今日は落ち着いて過ごせたね。一緒にご飯を食べたれたのが嬉しかったよ。
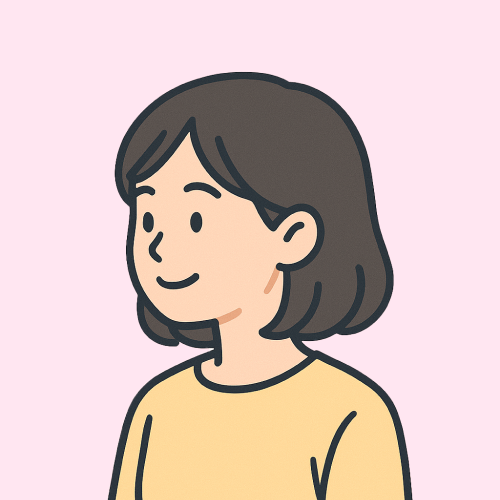
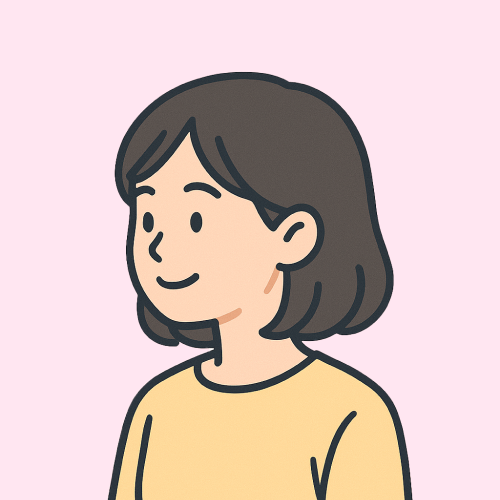
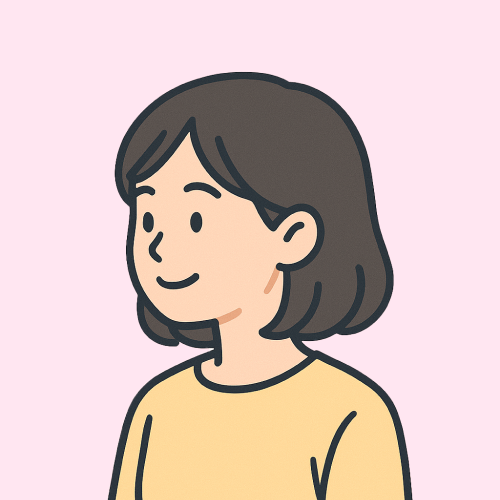
うん、今日はなんかちょっと楽だった



今日は落ち着いて過ごせたね。一緒にご飯を食べたれたのが嬉しかったよ。
「普通の日」をしっかり褒めて、大切にすることは最も当事者にとって重要なこと。
最後に|パートナーと当事者、二人に届けたいメッセージ
双極性障害と向き合う毎日は、当事者にとっても、パートナーにとっても、決して簡単な道ではありません。
お互いに「どうしてこんなにしんどいんだろう」「どうしたら上手く寄り添えるんだろう」と悩む瞬間が、何度も訪れているはず。
だけど、お互いに「ちゃんとしなきゃ」「ずっと支え続けなきゃ」と思い過ぎて、本当に大事なものを見失ってしまうことが、一番悲しいことだと私は思っています。
どちらか一方が我慢する関係ではなく、
無理をし過ぎない
疲れたら休む
嫌なことは優しく伝える
小さな嬉しいことを一緒に喜ぶ
そういう緩やかで、続けられる二人のペースを大切にしてほしいです。
一緒にいるために、離れる時間があってもいい。
支える側も、支えられる側も、どちらも幸せになってほしいです。
そんな気持ちを、私は皆さんに伝えたいです。
今日も最後まで読んでくれて、本当にありがとうございます
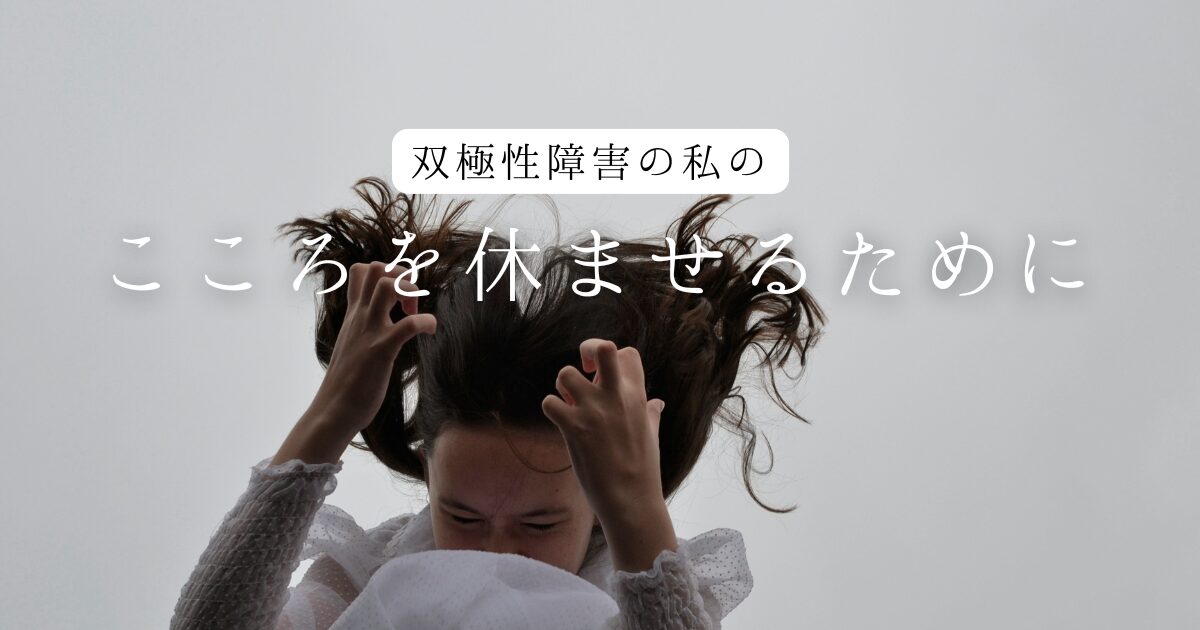

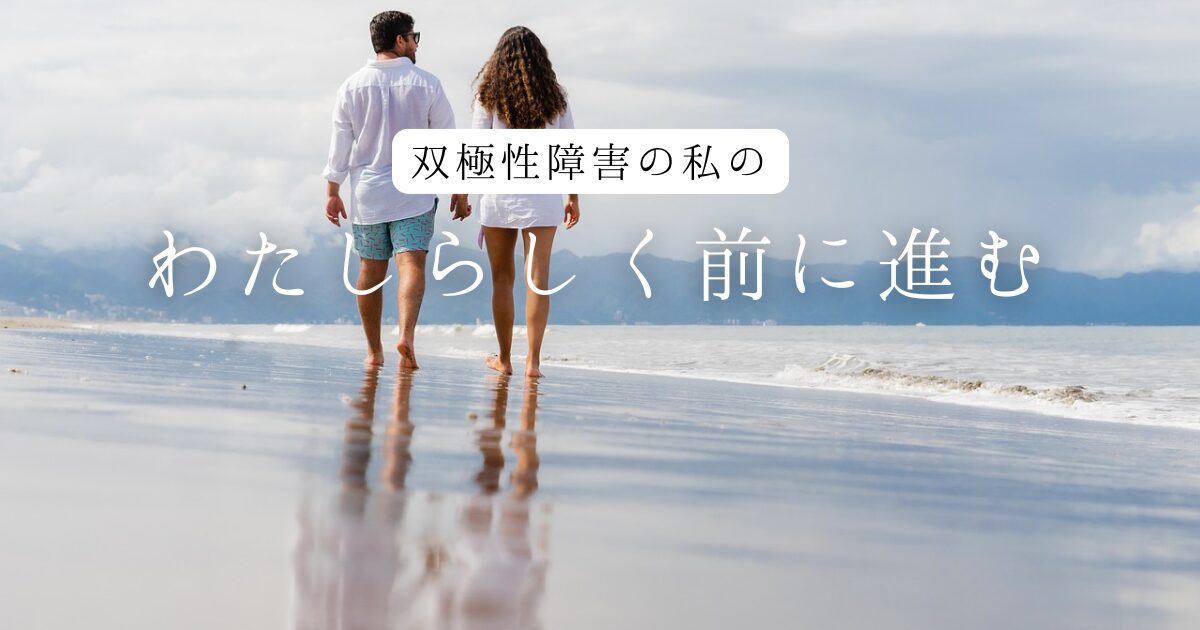
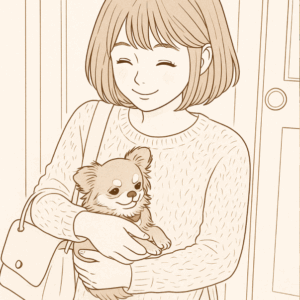
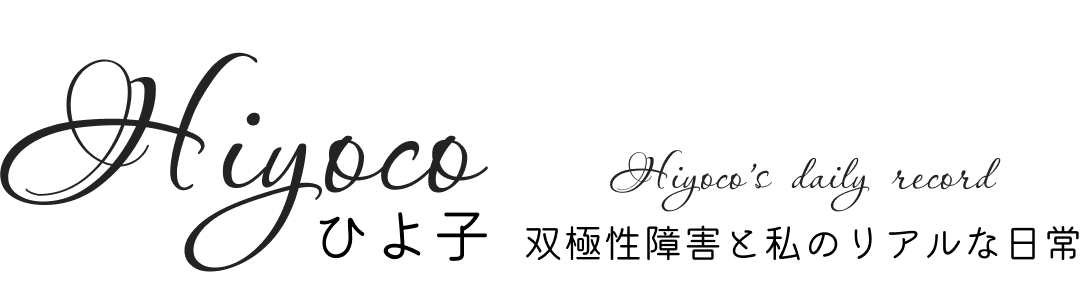
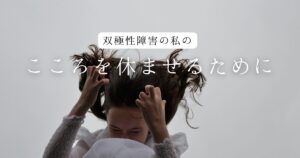
コメント