「もう無理かもしれない」「私まで壊れそう」
双極性障害のパートナーを支える中で、こんな気持ちになったことはありませんか?
双極性障害(躁うつ病)は、感情が激しく、突然の気分変動や衝突、予測不能な言動に苦しむことが多い病気です。
そしてこの病気は、本人だけでなく支える家族やパートナーの心まで深く傷つけてしまうことがよくあります。
実際に、日本うつ病学会の調査によれば、精神疾患を持つ家族を支える介護者のうち約4割が「精神的に限界を感じた経験がある」と回答しています。
また、「双極性障害 パートナー 離婚」はGoogleでも毎月多くの検索がされており、多くの人が同じように苦しみ、悩んでいる現実があります。
あなたは一人ではありません。
そして、あなた自身で壊れてしまう前に、取れる選択肢がきっとあります。
この記事では、双極性障害のパートナーを支えるあなたが「離婚したくなるほど苦しい」と感じたときに知っておいてほしい7つの心を守る対処法を、実例とともに【完全保存版】としてご紹介します。
「自分の気持ちを優先する」習慣を持つ(自己犠牲をやめる)
双極性障害のパートナーを支える人は、相手を優先しすぎて「共依存」に陥りがちです。
「私が頑張らないと」「私が支えなきゃ」という思い込みは、あなた自身を追い詰めてしまうことになりかねません。
そうならないために、小さなわがままや、ひとり時間を取ることは、むしろ必要不可欠です。
私たち夫婦も実は、「離婚」のワードは頻繁的に出ていたのです。夫も私もボロボロの状態にまで…
夫が崩れることもあり、しかし私はまだハイ状態。
このままだと”共倒れ”すると危機を感じた私は、ひとりで過ごす時間を提案しました。それが私たちにとって本当の意味で救われたんです。お互い泣くこともあって、夫には心では悪いなと思いつつも、自分を止められないのが現実。
この方法を試すことで少しですが、互いに心のゆとりができました。
パートナーを支えすぎて「共倒れ」していませんか?
双極性障害のパートナーを支える中で、「私さえ頑張れば、きっと治る」「私が我慢すればうまくいく」と思い込んでいませんか?
実は、多くの家族やパートナーがこの【自己犠牲】の罠に陥ります。
最初は愛情から始まっても、気が付けば、自分の感情を押し殺し、パートナーのために生きてしまっているのです。
その状態が続くと、うつや燃え尽き症候群を引き起こし、離婚したくなるほど苦しくなってしまう…。
支えるには、まずは自分を支えることが最優先です。
実践方法|小さな「自分優先」を生活に取り入れる
例①:1日15分だけ「自分のための時間」を作る
散歩、読書、携帯を見ない時間を作る。
パートナーが不安がっても「この時間は自分のため」と割り切る。
パートナーが話しかけても「この時間は譲らない」と決める。
朝のコーヒや紅茶タイムを設けて、気を他に向けてみる。
ポイント
自分だけの時間を確保することで、「私は私の人生を生きている」という感覚が戻り、パートナーと真摯に向き合うことができます。
例②:「NO」と言える練習をする
ポイント
小さなNOを積み重ねることで、大きなNO(離婚をするかどうか)の判断が冷静にできるようになります。
その結果、お互いにとってメリットが増えます。
「頼れる人」や「相談窓口」を確保する
ひとりで抱え込まないことが、離婚を防ぐ第一歩です。
例えば、精神保険福祉センターや家族会、オンライン(オフライン)相談を積極的に活用してみましょう。
実際に、支援を受けていた人のほうが、長期的にパートナーと良好な関係を築けやすいというデータもあります。
当事者ももちろん、頼れる人や相談窓口の確保は必要ですが、パートナーも一人間なので全部を受け止めてしまったりもします。
あなたが支えたい気持ちは十分本人には伝わっていますよ。
私も、突然夫に対して感情が激しくなって、突然の気分変動や衝突、予測不能な言動をしてしまうことも。
だけど、後になって「ごめんね」と少し冷静に戻った時に後悔と自分に対して悔しさが付きまといます。
だからこそ、何かあった時のために夫婦で事前に話しておくこともいいかもしれません。
ひとりで背負い込むほど心は壊れやすい
「誰にも話せない」「理解されない」と思い込み、孤独になっていませんか?
支える人が孤立すると、必ず限界が来ます。
実は、パートナーを支える家族向けの支援は、全国にたくさんあるのです。
支援者はあなたの悩みに真摯に寄り添い、「離婚したい」「逃げたい」という心の奥の気持ちも絶対に否定しません。
だからこそ、あなた自身が壊れるまで我慢はしないでほしいです。それが、大切な方のためとはいえ、我慢する必要は全くないのです。
実践方法|具体的な相談先とつながる
例①:家族会・支援センターを活用する方法
まずは、地域の精神保健福祉センターにお電話で相談してみてください。
あなたは一人では決してありません。相談することに抵抗やパートナーに申し訳なさを感じることもあるかと思いますが、前向きに”専門機関”に頼るのも二人にとって大切なことでもあります。
日本双極性障害協会の家族会や、地域の精神保険福祉センターに参加する。
月1回のオンライン相談会に参加するだけでも心理的負担が軽くなる。
ポイント
「支える仲間がいる」と思えるだけで、心の負担は確実に軽くなります。
例②:友人・家族・会社に「相談できる人」を一人持つ
信頼できる人に「ただ話を聞いてほしいだけ」と伝えておく。
「何も解決しなくてもいい。愚痴を聞いてくれるだけで助かるんだ」ということ。
ポイント
相談相手は「助言をくれる人」よりもあなた自身の「気持ちを受け止めてくれる人」が最も最適です。
境界線(バウンダリー)をしっかり持つ
躁状態やうつ状態が激しいとき、パートナーに振り回され過ぎない距離感を持つことが最も大切です。
「今日は私はこれ以上は話せない」「今はこれに付き合えないかも」とはっきり線を引くことは、二人の関係を守るためにも必要なこと。
お互いに距離感が近すぎると、いくら好きな相手であってもしんどくなることってありませんか?
夫が言っていたのですが、やはりお互いに境界線を引くことはお互いこ心のゆとりにもつながるということです。
私はそれを聞いて、本当にその通りだと痛感しました。
境界線とは簡単にいうと、「自分と他人の間に引く心の線」のことです。
例えば、どんな線引きがあるのかお話しします。
どこまでが自分の責任か?
どこからが相手の問題か?
どこまで付き合うか?どこからは付き合わないか?
双極性障害のパートナーを支えていると、この線が曖昧になりがち。
あなた自身が壊れてしまう原因にもつながってしまうので、お互いに線引きすることは必要です。
相手の問題を「あなたの問題」にしない勇気を持つ
双極性障害はのパートナーは、感情が爆発したとき「あなたのせいだ」と責めたり、過度に依存してくることがあります。
ここで大切なのは、相手の問題は相手のものであり、自分が全て背負う必要はない、という”線引き”です。
境界線を持っていないと、自分が当事者とともに共倒れしてしまいます。
実践方法|バウンダリーの作り方と伝え方
例①:感情的な攻撃から距離をとる言い方
「今はお互い冷静に話せないから、少し距離を置こう」
「その言い方をされるのは私は嫌かな。落ち着いたらまたゆっくり話そうね」
ポイント
怒りに巻き込まれないこと。離れる選択も「パートナーを守ること」に繋がります。
例②:安全な逃げ場を事前に準備する
実家、カフェ、ホテルなど「パートナーに行き先を知られない場所」を確保しておく。
家の中でも「自分の部屋」や「絶対に立ち入らないスペース」を作る。
ポイント
物理的に距離を取れる場所があると、「逃げてもいい」と自分に許可を出せます。
パートナーの病気を「正しく理解する」
双極性障害は、「甘え」でも「性格」でもありません。
一緒にいて、酷い時やましな日を繰り返し見ているあなたは思いたくなくても、
「もしかして、性格なんだろうか」
と、思い込んでしまうこともあるはず。
私の夫も、私があまりに暴言や怒鳴り声を聞いていると「本当は、怒る人?」と思うことが何度もあったと私に打ち明けてくれました。
その時の私はとても苦しかったです。
だけど、私と同じように支える側も苦しいということ。
あなた自身が全く苦しまないでいられる、のは難しいかもしれませんが、少しでもあなた自身がしんどくならないためにも病気の正しい理解は大切です。
夫は、私の口から病気のこと100パ%伝えることは難しい。
だからこそ、双極性障害の本や医療機関や病院の主治医に聞いたり、誤った理解のリスクをなくすことです。
そして、正しい知識を持つことで、「どうしてこんなことを言うんだろう」という苦しさがほんの少しでも和らぎます。
病気を知らないと「相手が悪い」と思い続けてしまう
双極性障害の症状(躁・うつ)は、「性格の問題」に見えてしまうがちです。
実際は脳の病気による気分障害ではあるので、本人もコントロールができないのです。それがいちばん当事者が苦しいことでもある…。
しかし、正しい理解がないと、パートナーの言動にずっと傷ついてしまい、怒りを抱えたままになってしまいます。
実践方法|病気理解の具体的ステップ
例①:家族向け書籍・医療情報を活用する
パートナーにおすすめ書籍
これだけは知っておきたい双極症 第3版 ココロの健康シリーズ
→この本は”双極性障害”を基礎から勉強できる本です。イラスト形式で分かりやすくまとめてくれているので、パートナーを支えるために読んでほしい一冊です。私も読んだんですが、一緒に読んだ夫は、心に刺さることが多かったと私に伝えてくれました。
→『ツレがうつになりまして。』とい映画があり、その映画を漫画家した本です。
夫とDVD視聴したのですが、号泣したほど現実的で”うつとは?”という観念でもかなり理解できる内容の映画でした。
パートナーの支えによって”うつ病”という病気に向き合う二人を描いているもので、私たち夫婦も互いに支え合う方法を学ぶことができたので、ぜひパートナーと一緒にみて見てください♪
その他に、医療情報を調べるときは、必ず医療機関監修サイト(例:うつ病学会 こころの情報サイト)を利用してみる。
ポイント
ネット情報は誤情報も多いので、信頼できる書籍・公的機関から学ぶことも重要です。
例②:パートナーと一緒に医師の話を聞く
「家族も同席したい」と事前に病院の主治医に伝える。
医師から直接説明を受けることで、家族の不安や心配事なども軽くすることができる。
ポイント
自分で勝手に調べるだけではなく、必ず主治医と情報をすり合わせしましょう。
「うつ期」と「躁期」でサポート方法を変える
うつ期は、そっと寄り添い、躁期は冷静に距離を取ることがポイント。
「うつの時だけが危ない」と思いがちですが、躁期も事故・浪費・衝動行動が増えるリスクが極めて高くなってしまうということ。
当事者それぞれが、うつ状態と躁状態に起きる症状やその症状の酷さも異なります。
その為、本人の状態もきちんと把握することと、その上でどういったサポートが適切なのか、というのが需要になってきます。
状況に合わせて柔軟に対応を変えることが、あなたの心を守る近道にもなるのです。
私の場合は、生理がある週の前後の重なって病気の症状が出た時は、怒りが激しくあり、物を投げたり、夫に対しての暴言が絶えないという状況になってしまいます。
反対に生理の週の前後以外の日は比較的穏やかではありますが、時々ストレスや心の不安手によって生理の週の前後のようになってしまうことも…。
もし、「パートナーの方の生理が酷いんです」という方がいれば、私から伝えたいのが、生理と症状が重なってしまうと生理の時に起こるPMS(月経前症候群)の症状が強く出ていることもあるので産婦人科に受診してもらうのもいいかもしれません。
そんな時、パートナーの方は、「生理でより情緒不安定になっているんだ」と優しく接してあげてください。
状態によって接し方を間違えると逆効果になる
双極性障害は、「うつ」と「躁」で必要な対応が全く違います。
うつ期に励まし過ぎるとプレッシャーになりますし、躁期に一緒に動いてしまうと危険行動を助長してしまうことがあります。
この病気で、最も大切にしてほしいのは、”双極性障害”という病気の正しい理解です。誤った理解をしたことで、命の危険が伴うということは忘れないでほしいです。
単なる風邪とは違って、うつ状態や躁状態に起きる症状がそれぞれ本人にとってどういう影響を受けるのかということ!
実践方法|状態ごとの見分け方と接し方
例①:うつ期の接し方(落ち込み・自殺念願が強い時)
ゆっくりした口調で話す。「一緒にいるだけで大丈夫だよ」と優しく伝える。
生活リズムを整えることを最優先する。無理に行動させないことが需要。
危険サイン
本人が「消えたい」「楽になりたい」「何も楽しくない」というた言動が頻繁に頻出する場合は、早急に主治医へ相談することです。
例②:躁期の接し方(テンションが異常に高い時)
衝動買いや借金、ギャンブル、突然の転勤や引越し話が出る場合は、必ずストップ。
冷静に、「それは今は決めずに、後でゆっくりお話しよう」と伝える。
危険サイン
”自分は無敵だ!”、なんでもできるとい言い出したら、即受診が必要です。
「離婚してもいい」と考える勇気を持つ
決して離婚を悪いことだとは思わないでください。
「離婚を考える=裏切り」ではなく、「自分の心を守るための選択肢」として持っておくことが大切です。
離婚を考えることで、逆に冷静に支え続ける余裕が生まれる場合もあります。
”離婚してもいい”と、思いながら支えるということではありません。そこは勘違いしないでほしいです。
夫も、「離婚」は現実的であっても考えていないと思っていないとは言え、心の限界がくると思ってしまうからこそ、「離婚しないように、離婚しないようにしなきゃ」と自分を追い詰めないために、いざという時のことを考えておく勇気は必要かなって思います。
離婚は「逃げ」ではなく「自己防衛」
多くの支える人が、「離婚を考える私はひどい人間なんだろうな」と自分を責めてしまう場面は多いのでないでしょうか。
でも、あなたが壊れてしまっては、あなたの大切な人やその周りの人は悲しいでしまいます。
当事者本人も、あなたを追い詰めたくて追い詰めているわけではないということ!
逆に、離婚を考えるようになったのは、あなた自身が大切な人を支えてきて、頑張った証なのですから。
自分を責めてしまうことも悪いことでないし、私はむしろ、自分のことをしっかり褒めてあげてほしいです。
なので、離婚を選択肢として持つことは、むしろ健全で、自分の心を守る行動の一つなのです。
実践方法|離婚を現実的に検討する準備
例①:離婚後の生活を紙に書き出してみる
住む場所、収入、サポートしてくれる人、家族の反応を整理する。
書き出すことで、「本当に離婚したいのか、今の逃げ場が欲しいのか」が現実的となって見えてくる。
私の場合は、離婚を互いに考えたこともあるのですが、離婚後は互いにどうするのか。を整理しています。
私は圏外だったので、地元に帰るのか。入院するのか。など割と明確に書き出していました。
突発的やその場の勢いで「離婚する」というのはお互いにやめてほしいです。
後悔が必ず残ってしまうから、そうならないために事前に考えておくことが大切です。
例②:法律相談・支援センターを事前に利用する
弁護士の初回無料相談を受けてみる(自治体で無料の場合あり)
女性センター・配偶者支援センターにも事前に相談。
私は、現在時点で”法律相談・支援センター”に相談したことはないのですが、人それぞれ「離婚」に対しての重さは違うので、あなた自身が前向きに考えるのであれが、当事者本人に対して申し訳なさを感じる必要はないと思っています。
もし、相談するのであれば当事者本人に相談することを軽く伝えた上で行く方がいいかもしれません。
ポイント
「離婚の選択肢を知っている」というだけで、気持ちが少しでも冷静になることができます。
パートナーとの「未来図」を一度、見直してみる
双極性障害は、一生付き合う可能性のある病気です。
だからこそ、「私たちはこれからどうしたらいいのか」「私はこの先そう生きたいのか」を定期的に見つめ直すことが必要なのです。
私たち夫婦もその壁には何度もぶつかってきました。「本当に一緒にいて互いにとってこれが正解なのかな。」と夫も私も同じ気持ちでした。
はじめにお伝えした通り、支える側もこの病気は”精神的に限界がくる”ともよく言われているくらい簡単に向きあるようなものでもないということ。
いくら好きな相手であっても、人の心の限界を上回ってしまうと、「一緒にいることが嫌」と思ってしまうもの。
だからこそ、私が実際に苦しんで、、苦しんで、、今思うことはお互いにしっかり意見をぶつけ合うことが大切だということです。
私たちは苦しいことの方が多いけど、「それでも一緒に居たい!!!」という気持ちが一緒だったこと。
それが、話し合うことで確信に変わったので、一緒にいられるために、お互いが潰れそうな時のために、
「私の病気が落ち着いたら、いっぱい旅行行こうね。」
「いずれは、子ども授かって笑顔溢れる家族になろうね。」
と、未来への楽しみをお互いに作ったことで、「離婚」というワードは当時よりは少しだけですが減りました。
なので、二人で未来を話し合えるようになったときに、私は”新たな信頼関係が生まれる”かもしれないということです。
二人でこれからどうしたいのかを話し合うことも大切
双極性障害は、長く付き合っていく病気なので、「一生一緒にいる」と思い込んでしまうと苦しくなることも時にあるはず。
まさに夫も私もその一人でした。
「好きで結婚したはずなのに…」と自分を責めてしまいがち。
私は、自分がこの病気になったことで、そう思わせたと悔やんで、苦しんで、落ち込んでと悪循環に…。
その姿を見た夫は、何も言えなかったと当時のことを暗い顔で話してくれました。
そもそも夫婦というのは、離れることは簡単にできますが、何よりも一緒に長くいるというのは難しいことでもあります。
だって、パートナーは真っ赤な他人なのだから!
人と人は、「離れよう」と言えば離れることはできる!
そうたらないために今後、お互いにどうしたいのか、を短期と長期に分けて話し合い、未来図を修正していくことが必要です。
実践方法|未来を現実的にすり合わせる
例①:短期目標を立てる
「今月は週一回で一緒に外出する」「次の通院には一緒に行く」
小さな約束をクリアにして、お互いに達成感を持つ。
私たち夫婦は、常に”一緒に”◯◯しようね。は口癖のように夫が伝えてくれています。
それって当事者本人からすると、自分の存在意義を再確認することきっかけにもなるし、支えるパートナーからしても、何か一緒にすることで当事者本人の”大切さ”を再確認することにもつながり、互いにとって大切な瞬間になります。
例②:長期目標を話し合う
「2年後にどうなっていたいのか」「子どもを持つかどうか」など。
ここで意見が食い違う場合は、パートナーの希望と自分の希望が違うことを受け止める。
私たちは、当事者の病気のことで一杯一杯になりがちです。
だからこそ、目の前のことではなく、未来の話を二人でお話をすることで、未来目標を叶えるためにお互いが無理なく程々に頑張れる気がします。
ポイント
未来は、柔軟に変えても良いという前提を持つと、気持ちがお互いに軽くなっていきます。
最後に|パートナーに向けたメッセージ
あなたは、ここまで本当にたくさん大切な人のために頑張ってきたと思います。
時には、「離婚したい」「もう無理かもしれない」と感じることがあっても、それはあなたが弱いからでも全くありません。
むしろ、あなたが一生懸命に支えてきた証なのです。
どうか、あなた自身の心も大切にしてください。
あなたが笑えること、あなたが安心できること、それが一番大事です。
支えることは、離れないことだけじゃない。
時には離れる勇気も「支え方のひとつ」でもあります。
あなたの幸せも、あなたの未来も、大切にしていいんです。
この記事が、あなたの心が少しでも軽くなるきっかけになれば嬉しいです。
ゆっくりで、大丈夫です。あなたの幸せを、心から願っています。
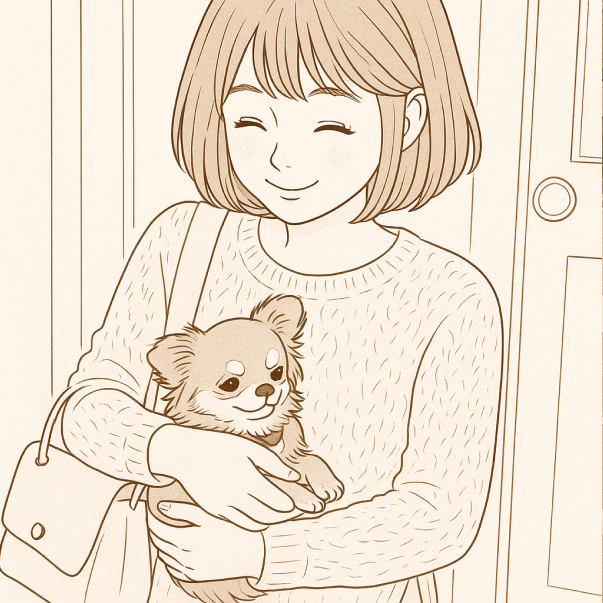 ひよ子
ひよ子最後まで読んでくださってありがとうございます。
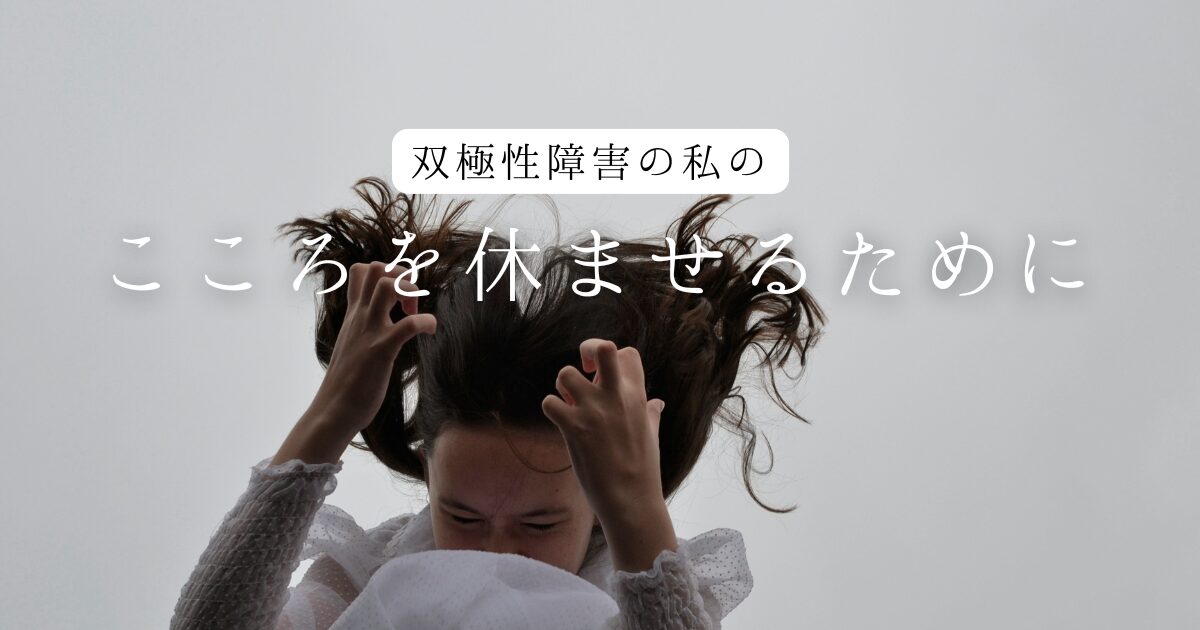

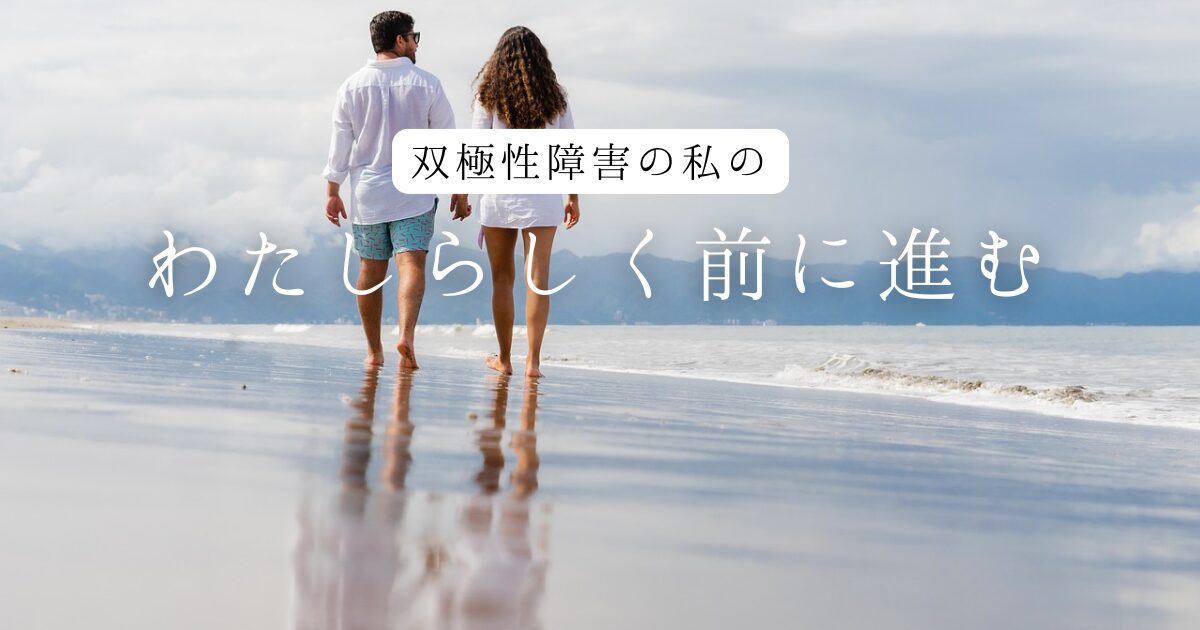
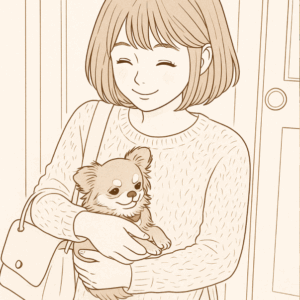
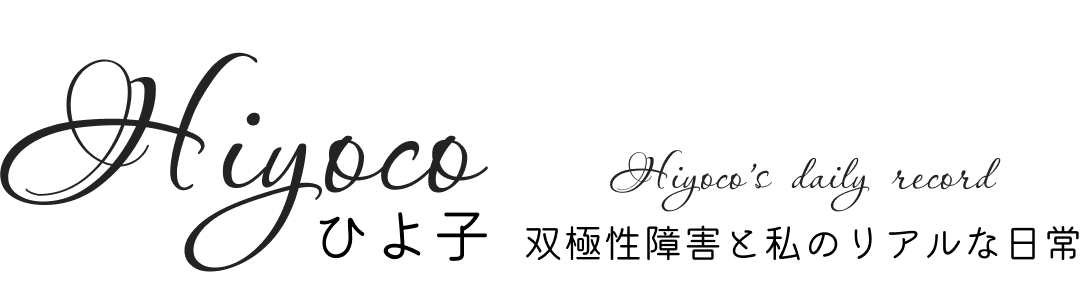
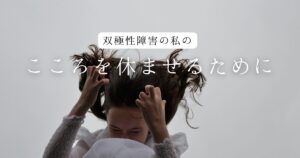
コメント